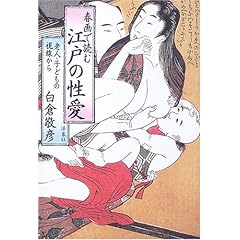『春画で読む江戸の性愛―老人・子どもの視線から』(洋泉社)
『春画で読む江戸の性愛―老人・子どもの視線から』(洋泉社)現代社会でしばしば見受けられるセックスに関する歴史的な認知のひとつに、「昔の人は性に対して厳格だった」とか、「貞操観念が強かった」というものがある。
しかし、史料や文献を紐解いてみると、縄文時代から明治維新前夜まで、大半の日本人がセックスというものに対して、非常に寛容だったということが瞬時に判明する。言い方を変えれば、日本人は歴史的に貞操観念など無いに等しい民族であった、と表現しても過言ではないのである。
たとえば、江戸時代の記録を見ると、庶民がセックスを娯楽、または日常的な享楽として大いに楽しんでいたことがよくわかる。
まず、日本にはセックスに対して罪悪と見る倫理観が歴史的に存在しない。『古事記』や『日本書紀』の時代から、セックスを単なる生殖行為ではなく、生活を楽しむためのライフスタイルのひとつとして考えているのが、わが国の伝統的な意識なのである。
それをうかがわせる史料は数多い。たとえば、4代目将軍徳川家綱の幕臣で、有名な儒学者でもある荻生徂徠(おぎゅう そらい)も「セックスは庶民にとって楽しみのひとつ」という趣旨の文章を書き残している。また、20世紀初頭のドイツの日本文化研究家フリードリヒ・S・クラウスも著書『名著絵題 性風俗の日本史』(河出書房新社)のなかで、「(日本では)童貞、あるいは処女というものは、価値が低いか、またはまったく価値が無いに等しい」と述べ、ヨーロッパとの価値観の相違を比較している。
こうした歴史的な素地があるのだから、心身ともに健康な若者たちが性に興味と行動を生じないわけはない。実際、当時は10代半ばともなれば男女ともにセックスを楽しんでいたのが実情のようである。農山漁村部では「若衆宿」などの若者たちが共同作業をしながら知り合うスペースがあり、自由恋愛にしてフリーセックスのシステムである「夜這い」も地域の慣例として行われていた。
一方、都市部でも知り合った若い男女が性的関係になることは珍しくなく、しかもとがめられることも無かった。時代劇などで「不義密通は重罪」などとして、現代でいう不倫が厳罰に処せられるのを見て、「江戸時代は無軌道なセックスはご法度だったのか」などと理解するのは早合点というものである。
たしかに、婚姻者が決められた相手以外にセックスしてしまうことは厳しい取り締まりの対象だった。しかしそれも、儒教の「貞女は二夫にみまえず」、つまり貞節な妻は一人の夫だけ愛するべしという考えに基づいたものであり、決して処女性を重視したものではなかった。
したがって、結婚していないフリーの男女にとっては、恋愛もセックスも本当に自由だったのである。だから、結婚前の若い女性がセックスしたとしても、親が「娘がキズモノになった」などと考える感覚は、存在しなかったのである。
処女性を清らかで価値あるものと考えるようになったのは、明治維新によってキリスト教が伝来し、詩人で評論家の北村透谷が『処女の純潔を論ず』などの作品を書くようになってからのことである。
だが、そうした「処女尊重、セックスは汚れ」という意識が広まったのは、都市部や一部知識階級に過ぎなかった。「夜這い」その他の日本固有の慣習は、農山漁村部で戦後まで受け継がれていくこととなるのである。
見られてナンボ?